 在来種
在来種 ツツジが昔ヨーロッパに渡り「アザレア」になって、わが国に里帰り
わが国のサツキやヤマツツジ等が江戸時代に品種改良され、江戸末期から明治時代にイギリスにもたらされた。明治末から大正時代頃にベルギーを主にヨーロッパで品種改良されアザレアが誕生。アザレアという名は、この品種改良して美しく創り出された常緑性ツツジの総称。
 在来種
在来種 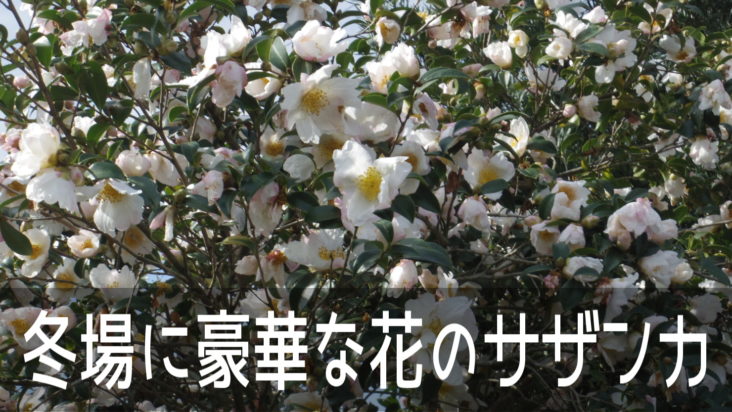 在来種
在来種  在来種
在来種  在来種
在来種  在来種
在来種  在来種
在来種  在来種
在来種  在来種
在来種 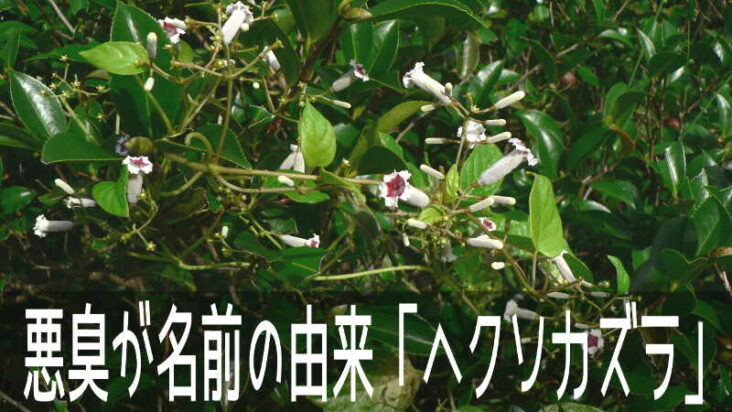 在来種
在来種  在来種
在来種